 弥生以前
弥生以前 あまりにも大きな池
夕暮れが早くなってきた。日が暮れると早く帰宅する気になるから、それはそれでよい。しかし時に「こりゃ時間が足りんわい」と焦りに焦るまくることがある。そんな時、「湖山長者(こやまちょうじゃ)」という人は、沈む太陽を金の扇で招き返し、田植えを強引...
 弥生以前
弥生以前  戦後
戦後  幕末
幕末  明治
明治  飛鳥
飛鳥  江戸前期
江戸前期  戦後
戦後 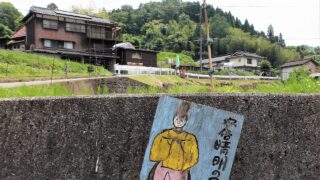 平安
平安  明治
明治  平安
平安