 江戸前期
江戸前期 美作に消えた天皇家
昭和史研究の第一人者として知られる保阪正康氏の著書に『十九人の自称天皇』がある。熊沢天皇、外村天皇、佐藤天皇、竹山天皇、三浦天皇など、戦後たくさんの自称天皇が出現したという。その多くは南朝の末裔だと称したが、確かに、後南朝の歴史はほとんど闇...
 江戸前期
江戸前期  江戸前期
江戸前期  江戸前期
江戸前期  江戸前期
江戸前期  江戸前期
江戸前期 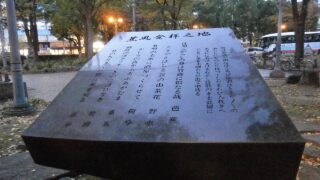 江戸前期
江戸前期  江戸前期
江戸前期  江戸前期
江戸前期  江戸前期
江戸前期  江戸前期
江戸前期