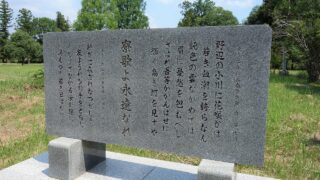 大正
大正 さはれ吾等がかんばせに
コロナ禍で歌うことさえ憚られるようになった。合唱さえ自粛しているのだから、寮歌を肩組んで放吟するなどもってのほかである。とはいえ、今どき寮歌が歌われているのだろうか。ひと昔前の印象はあるが、「栄冠は君に輝く」のような応援歌だから、今聴いても...
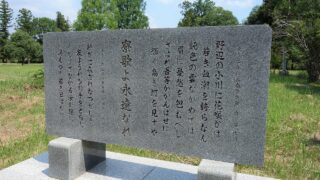 大正
大正  鎌倉
鎌倉  明治
明治  鎌倉
鎌倉  古墳
古墳  神話
神話  奈良
奈良  南北朝
南北朝  江戸前期
江戸前期  神話
神話