 飛鳥
飛鳥 星降る真星の星神社
星降る夜という素敵な表現がある。漆黒の宇宙に散りばめられた星々が空を満たしている光景が思い浮かぶ。本当に星が降ったという伝説もある。いちばん有名なのは山口県下松市で「下松発祥之地 七星降臨鼎之松」という石碑が建てられている。本日は岡山県の降...
 飛鳥
飛鳥  弥生以前
弥生以前 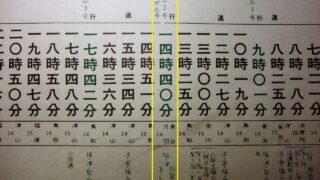 安土桃山
安土桃山  安土桃山
安土桃山  南北朝
南北朝  江戸後期
江戸後期  安土桃山
安土桃山  古墳
古墳  安土桃山
安土桃山  戦国
戦国