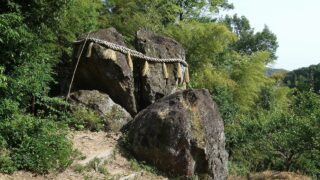 神話
神話 岩を通した皇后の矢
岩には不思議な魅力がある。大きさ、形のよさから微妙に動く岩まで楽しむ要素は多い。その不思議さに神が宿ると考えられたり、英雄と関連付けられたりする。そして信仰の対象となっていく。今日は見事に割れた巨岩にまつわる伝説を紹介しよう。姫路市西脇に「...
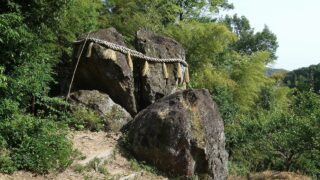 神話
神話  明治
明治  戦国
戦国  安土桃山
安土桃山  神話
神話  源平
源平  古墳
古墳  幕末
幕末  古墳
古墳  鎌倉
鎌倉