 幕末
幕末 3日で終わった討幕の先駆
世直しといっても、まつりごとを私する奸物を除くのは「改革」だが、権力そのものを否定するのは「革命」である。そういう意味では桜田門外の変と天誅組の変・生野の変は指向の異なる動きである。今回は生野の変を取り上げるが、これは幕政改革を目指したもの...
 幕末
幕末  明治
明治  江戸中期
江戸中期  明治
明治  安土桃山
安土桃山  戦国
戦国 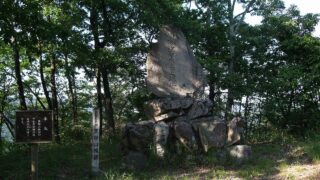 戦国
戦国  江戸前期
江戸前期  古墳
古墳  平安
平安