 江戸後期
江戸後期 天神さまの細道ぢゃ
本当は恐い童話とか、本当は恐いわらべ歌というのがあるらしい。実は残酷だったり何かを暗示すると解釈されたりして、意外性があるところがウケるのだろう。今日扱うのは『通りゃんせ』である。歩行者用の青信号の音楽として有名だ。とおりゃんせ、とおりゃん...
 江戸後期
江戸後期  弥生以前
弥生以前  明治
明治  幕末
幕末  戦後
戦後 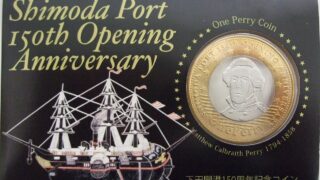 幕末
幕末  奈良
奈良  戦前戦中
戦前戦中  戦後
戦後  幕末
幕末