 江戸中期
江戸中期 寛政戊午重三禊飲于此
謎の芸術家バンクシーが器物損壊を問われないのは、価値を台無しにする落書きではなく、価値を付加するアートだからだという。分かったようで、どこか腑に落ちない心持ちだ。しかし、似たような例は我が国にもある。美しい渓流で宴を開いた拙斎先生。興が乗っ...
 江戸中期
江戸中期  弥生以前
弥生以前  室町
室町  江戸前期
江戸前期  戦国
戦国 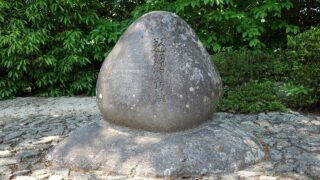 幕末
幕末  鎌倉
鎌倉  弥生以前
弥生以前  戦後
戦後  古墳
古墳